
外国人社員が日本で就労するためには、在留資格(就労ビザ)が必要です。
しかし、在留資格は出入国在留管理局の指定する必要書類を提出したからと言って、必ず取得できるというわけではありません。
また、一度でも不許可になってしまうと、その事実が出入国在留管理局に記録され、再申請を行う際にも不利な事実として扱われる場合があります。
このページでは、在留資格が不許可になる原因を紹介していきます。
もし、これらの不許可原因に該当し許可を取得するのが難しい場合、申請したが不許可となってしまった場合には、専門家に相談することを強くお勧め致します。
不許可になった場合に生じる損失

在留資格申請が不許可になった場合、外国人・雇用主双方に、大きな損失が生じます。
外国人
外国人側としては、新たに再就職先を探さなくてはならず、再就職先が見つからない場合には、帰国を余儀なくされます。日本に配偶者やお子さんがいるような場合には、家族と離れて生活せざるを得ません。
雇用主
雇用主側としては、採用活動に投じた時間・労力・資金が無駄になり、新たに採用活動を始めなくていけません。また、このような外国人を解雇することに伴い、トラブルが生じたり、労働紛争に巻き込まれる可能性があります。
一度でも不許可になると許可を取るのが難しくなる

一度不許可になると、許可取得の難易度は上がります。
その理由は、一度でも不許可になると、それ以降の提出書類に信憑性がなくなり、出入国在留管理局が不信感を抱くためです。
不許可になった場合には、提出書類の内容を変えて再申請をすることになります。
しかし、同じ雇用主・同じ外国人であるにも関わらず、短期間で書類の内容が変わるということは不自然で、提出書類の信憑性は落ちます。
出入国在留管理局としても、「書類の上では不許可原因が解決されたように見えるが、実態は一回目の申請と変わっていないのでは」という不信感を抱きます。
不許可のあとの申請は、この不信感を払拭しなくてはいけなくなるため、許可取得の難易度が上がるのです。
在留資格申請が不許可になる5つの原因
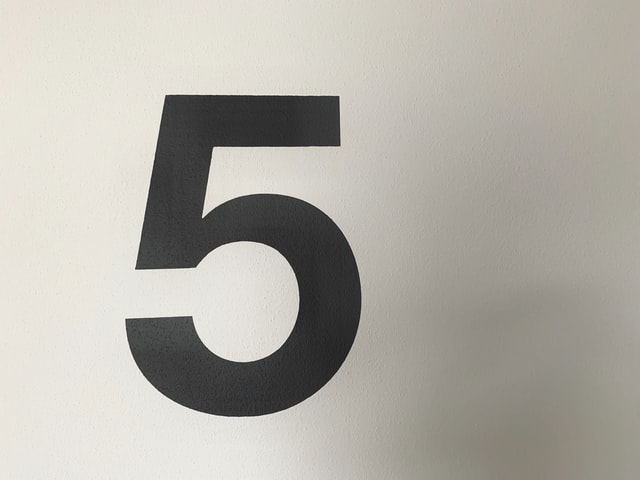
外国人を雇用することが、外国人・雇用主の双方にとってメリットになるように、また、一回の申請で許可を取得するためにも、不許可になる原因をしっかり抑えて、申請書類・申請資料を作成しましょう。
申請内容に虚偽がある
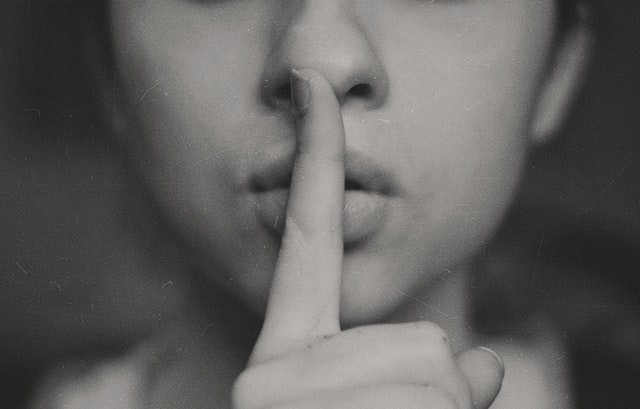
在留資格申請において、最もやってはいけないことが虚偽の申請をすることです。
虚偽の申請とは、「事実とは異なる申請をすること」、「不利益な事実を隠して申請をすること」の2つを意味します。
出入国在留管理局は、申請書類・資料に重大な虚偽があれば、不許可の方向で審査を行います。
「少しくらい嘘を書いてもばれないだろう…」、「不利益な事実は書かないでおこう…」と考える方がいるかもしれませんが、出入国在留管理局が数十年に渡って培ってきた審査の網をかいくぐることは不可能と考えるべきです。
刑事訴追の可能性も
虚偽の申請書・資料を提出して在留資格を取得した場合、
- 在留資格不正取得罪(出入国管理及び難民認定法第70条第1項第2号の2:3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金)
- 営利目的在留資格不正取得罪(出入国管理及び難民認定法74条の6:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
と言った非常に重い罪に問われる可能性があります。
また、不許可となり在留資格を取得できなかった場合でも、
- 公正証書原本不実記載罪(刑法第157条:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
の未遂罪に問われる可能性があります。
事実と異なる申請をしたり、不利益な事実を隠すことは絶対に避けて下さい。申請が不許可になるだけでなく、会社や事業そのものを危険に晒すことになってしまいます。
申請書類に矛盾がある
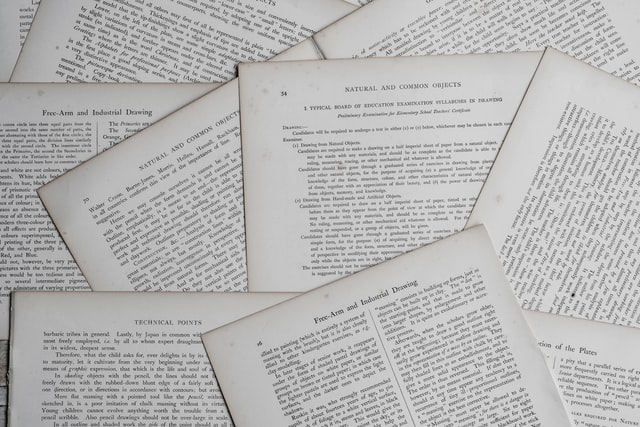
申請書類に矛盾する事実が含まれている場合、不許可の方向で審査が行われます。
なぜなら、矛盾するどちらかの事実が虚偽であると判断されるためです。
また、出入国在留管理局は審査の際、過去に提出された書類も必ず確認します。
そのため、今回提出する書類と外国人が過去に提出した書類が矛盾する場合も、不許可になる可能性が高くなります。
単なる書き間違い、記憶違いという場合もあるかもしれませんが、矛盾している以上は合理的な説明を求められます。もし、提出書類に矛盾した事実があった場合、説明を裏付ける合理的な資料を提出しましょう。
許可を取得するための要件を満たしていない

許可を取得するための要件を満たしていない場合は、不許可の方向で審査が行われます。
出入国管理及び難民認定法には、「相当の理由がある時に限り、許可することができる」と規定されており、許可を取得するためには「相当の理由がある」ことが必要になります。
許可を取得するための要件を満たしていない場合、「相当の理由がない」と判断され、不許可になる可能性が高くなります。
出入国管理及び難民認定法 第二十条第三項(在留資格の変更)
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
e-Gov 出入国管理及び難民認定法 第二十条
出入国管理及び難民認定法 第二十一条第三項(在留期間の更新)
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
e-Gov 出入国管理及び難民認定法 第二十一条
すでに雇用契約を交わした外国人が要件を満たしていない場合には、要件を満たしてから申請するようにしましょう。
事業が小規模・不安定

事業が小規模・不安定である場合、不許可の方向で審査が行われます。
会社の取り扱い業務量が少ない場合や外国人を雇用するだけの体力がない場合、出入国在留管理局としては「本当に雇用するのか」という疑念を抱きます。
つまり、自社で雇用すると見せかけて、他社に外国人を斡旋するような偽装雇用が行われるのではないかと考えるのです。
このような違法行為は日本人の雇用を奪うことに繋がるため、不許可になる可能性が高くなります。
最高裁判所も以下のような判例を出しているため、出入国在留管理局は日本人の雇用や労働市場の安定を重視した審査をします。
(前略)法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたっては、(中略)国内の治安と善良な風俗の維持、保険・衛生の確保、労働市場の安定など国益保持の見地に立って、(中略)時宜に応じた的確な判断をしなければならない(後略)
最高裁判所 最高裁判所判例集
事業が小規模・不安定である場合には、外国人に十分な業務量があること、安定的・継続的に雇用できることを証明する資料を一緒に提出しましょう。
採用した留学生が違法なアルバイトをしていた場合
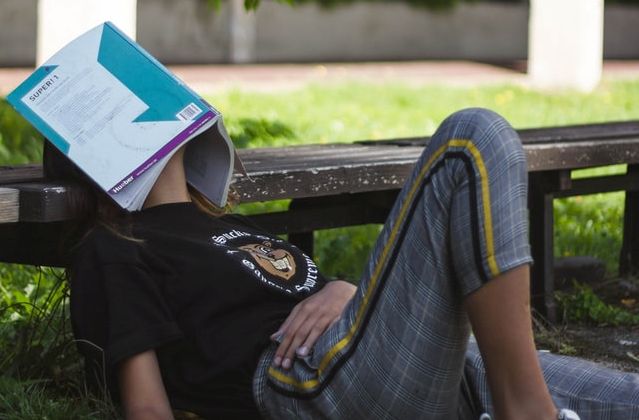
採用した留学生が、出入国在留管理局から許可を受けずにアルバイトをしていたり、許可の範囲を超える長時間のアルバイトをしていた場合、「違法なアルバイトをしていた」と判断され不許可になる可能性が高くなります。
留学生本人は母国にいたときと同じ感覚でアルバイトをしていたかもしれませんが、これらの行為は出入国管理及び難民認定法に違反しています。
法律を執行する出入国在留管理局が、違法行為を見逃すことはありません。
このような場合、許可を取得することが非常に難しくなります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
上記の不許可原因に該当してしまった場合、外国人が在留資格を取得するのは難しくなります。
専門家以外の方が申請した場合、許可を取得できる可能性は低いでしょう。
しかし、これらの不許可原因に該当しているからと言って、必ずしも許可の可能性がないわけではありません。
採用した外国人の人柄・個性・能力に惹かれ「どうしてもこの外国人を雇用したい」、「自社の将来の戦略に必ず必要となる」とお考えでしたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。
外国人雇用に必要な法務大臣の許可を、適法に・安全に・迅速に取得できるよう、徹底的にサポートいたします。
東京品川で無料相談実施中!
無料相談のみもOK。お気軽にお問い合わせ下さい。
